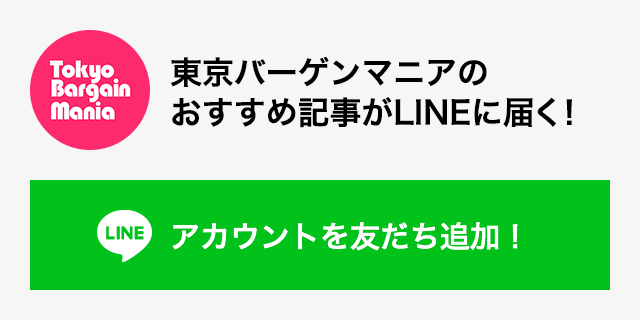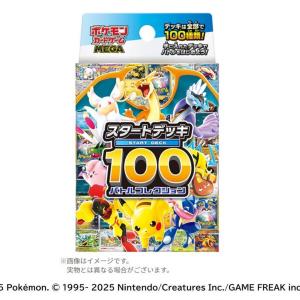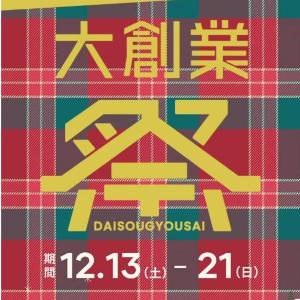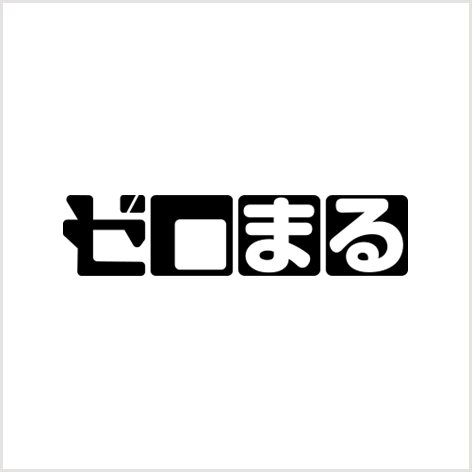スマホばかりで本が読めない...。なぜ仕事と読書の両立は難しい?現代人の"あるある"悩みに迫る。
「全身」をやめて「半身」で働く
もう1つのキーワードに、「半身(はんみ)」があります。「半身」とは、「さまざまな文脈に身をゆだねる」こと。「働きながら本を読める社会」をつくるために三宅さんは、「全身全霊をやめませんか」「半身で働こう」と読者に語りかけます。そうすることで、自分の「文脈」の半分は仕事に、もう半分はほかのことに使える、としています。
この「文脈」というワードも印象的でした。自分がこれまで生きてきた「文脈」があるように、他者にも、そして一冊の本の中にも「文脈」がある。こうした仕事以外の「文脈」を自分の中に取り入れることが大切で、それこそが「健全な社会」であると、熱く書かれています。
自分の知らなかったことがじつは現代の常識になっていると知り、衝撃を受けた経験はありませんか。そのつもりはなくてもシャットアウトしている「文脈」は、意外とあるのかもしれません。
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」に対する、「○○だから読めなくなる」「△△したら読めるようになる」という答えだけを知りたい読者にとって、本書は正直、じれったい構成かもしれません。全体のおよそ3分の2まで読んだところでようやく、核心にたどりつくからです。
ただ、今回の読書体験をとおして、なるほど、これが「ノイズ」を受け入れる、「文脈」を自分の中に取り入れる、ということなのだなと思いました。スマホでも何でも、視界に入っていても見ていない物事がいかに多いか、身につまされます。
忙しいとなかなか本を開く気になれないものですが、読みたい気持ちがないわけではないんですよね。仕事と読書の両立が気になって読みはじめたら、思いがけない展開が待っていて、読書の面白さを再発見できる一冊です。
(Yukako)

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』三宅香帆 著(集英社)
■目次
まえがき 本が読めなかったから、会社をやめました
序章 労働と読書は両立しない?
第一章 労働を煽る自己啓発書の誕生――明治時代
第二章 「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級――大正時代
第三章 戦前サラリーマンはなぜ「円本」を買ったのか?――昭和戦前・戦中
第四章 「ビジネスマン」に読まれたベストセラー――1950~60年代
第五章 司馬遼太郎の文庫本を読むサラリーマン――1970年代
第六章 女たちのカルチャーセンターとミリオンセラ――1980年代
第七章 行動と経済の時代への転換点――1990年代
第八章 仕事がアイデンティティになる社会――2000年代
第九章 読書は人生の「ノイズ」なのか?――2010年代
最終章 「全身全霊」をやめませんか
あとがき 働きながら本を読むコツをお伝えします
■三宅香帆さんプロフィール
みやけ・かほ/文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない―自分の言葉でつくるオタク文章術―』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。
画像提供:集英社
※この記事による収益の一部は、東京バーゲンマニアに還元されます。
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。