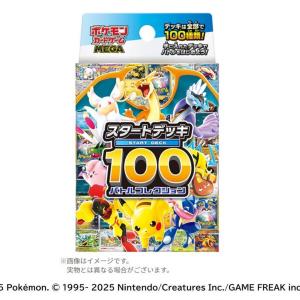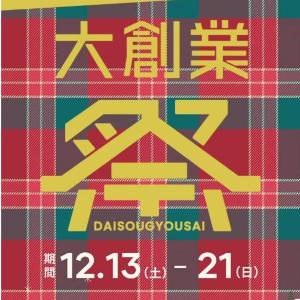読書って「ノイズ」だらけ...だけども...
本書は一気に明治までさかのぼり、大正、昭和戦前・戦中、1950~60年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代と、日本人の仕事と読書のあり方の変遷をたどります。そして最後に「働きながら本を読める社会」をつくるための提言が書かれています。
まず、キーワードの1つ「ノイズ」を見てみましょう。ここでいう「ノイズ」とは、「他者や歴史や社会の文脈」のこと。読書離れといわれて久しいですが、じつは1990年代から自己啓発書の市場は伸びているそうです。それは自己啓発書が、自分でコントロールできる行動の変革を促し、自分ではコントロールできない社会を「ノイズ」として除去するものだから。
しかし、読書はそもそも、自分が知らないことを取り入れるもので、ページをめくった先に何が待っているかわかりません。つまり「アンコントローラブルなエンターテインメント」で、「ノイズ」だらけなのです。
2000年代、インターネットによって生まれた情報が台頭しました。読書で得られる知識とインターネットで得られる情報の違いは、「ノイズ」の有無。スマホは見られるのに本を読めないのも、インターネットは「ノイズ」なしに自分が知りたいことだけを知れるからだと、三宅さんは指摘します。そのうえで強調しているのが、「ノイズ」の大切さです。
大切なのは、他者の文脈をシャットアウトしないことだ。
仕事のノイズになるような知識を、あえて受け入れる。
仕事以外の文脈を思い出すこと。そのノイズを、受け入れること。
それこそが、私たちが働きながら本を読む一歩なのではないだろうか。
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。