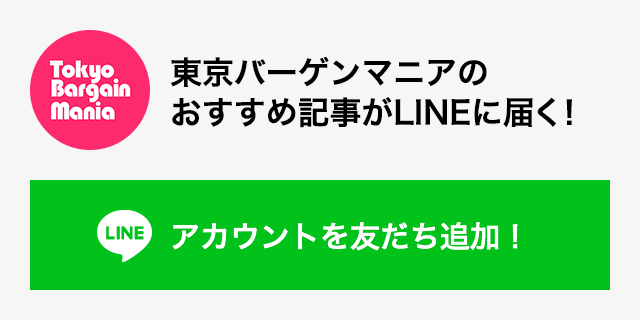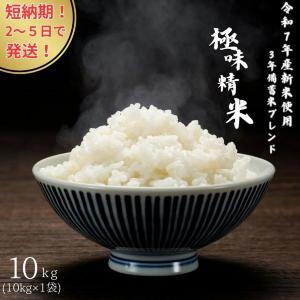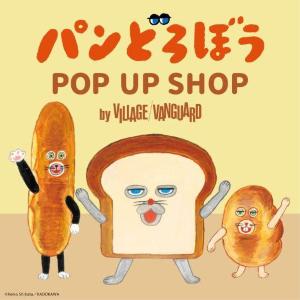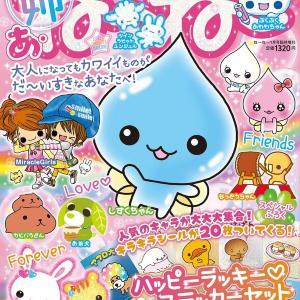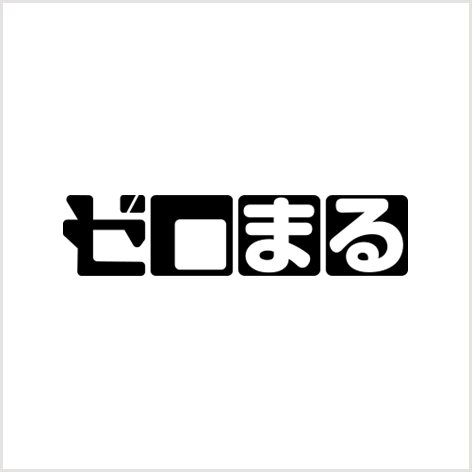映画「日本の悲劇」小林政広監督インタビュー/「音が主張する映画」を作るため、ワンカットで長回し撮影
ひとつ屋根の下で暮らす父と息子。がんを患い余命いくばくもない父親は、自室に閉じこもると、自らミイラ化する意志を息子に伝える。意表をつく行動に驚き、動揺した息子は懸命に説得を試みるが、父親は耳を貸さない。解雇されて収入のない息子は、父親の年金で生活していた。父親は「自分が死んだ事実を隠し、年金をもらい続けろ」と息子に言うのだが――。
小林政広監督が「春との旅」(10)に続き、再び仲代達矢主演で撮った「日本の悲劇」。長回しのワンカット撮影を中心に、ほぼ2人だけで演じられる物語は、舞台劇を見るような緊迫感に満ちている。小林監督は「"音が主張する映画"を作るため、ワンカットのフィックスで長回し撮影した」と語った。
仲代の起用により、画面が「静」から「動」に
――父親役の仲代と息子役の北村一輝の息がぴったり合っていた。キャスティングは最初から決まっていたのですか。
父親役は仲代さんに決まっていました。しかし息子役は最後まで決まらなかった。母親、奥さん役を誰にするかによって、息子の年齢が変わる。母親役が大森(暁美)さん、奥さん役が寺島(しのぶ)さんに決定した段階で、北村(一輝)君に決めました。
――「春との旅」もそうでしたが、仲代のいかにも役者らしい"作り込んだ演技"に圧倒されました。以前の監督作品に見られた"自然体の演技"とは異質。彼との出会いで、演出法が変わったのでしょうか。「春との旅」の会見で「昔は嫌いだった黒澤明が、今は好きになった」と発言したことと符合するように思いますが。
ヨーロッパの映画が手練手管で見せる"インテリ映画"ばかりになったことに不満を感じていました。自分のそれまでの映画で、持っている引き出しを出し尽くしたように思えた。「フリック」(04)を作った時、自己模倣していると痛感したんです。そこで昔の日本映画を見直した。成瀬、小津、最後に一番敬遠していた黒澤明監督。デビュー作の「姿三四郎」(43)から見ていった。実は黒澤作品はほとんど見ていなかった。何か権威主義みたいなものに反発を感じていたんです。
「七人の侍」(54)の面白さも再発見しましたが、特に「乱」(85)がすごいなと。公開時に見た時はわけが分からなくて、途中で寝てしまったんですが(笑)。しかし見直すと、実験精神にあふれた力強い映画でした。
「春との旅」のキャストを考えていた時期、「乱」の城から焼け出されて気が狂う主人公と、「春との旅」の主人公が重なった。ホン(脚本)自体は、小津監督の「東京物語」(53)的な話で、演出もその方向でと思っていたのですが、「乱」を見て気が変わった。仲代さんがあの感じで演じたら、全然違う映画になるなと。静的な画だったのが、仲代さんですごく動的な画に変わっていく、と確信したんです。
仲代さんは、面白く見せることにはすごく長けている。わざとらしさと紙一重のところで演じる。長年の経験から来るのでしょうが、微妙なさじ加減を心得ているように見える。計算しているのか分からないところがある。(人間の内面を重視・追体験する)メソッド演技とも違う。
「春との旅」では本番中につんのめりそうになり、車にひかれそうになった。僕は思わず大声を出した。仲代さんに駆け寄り「ひょっとして、わざとやったんですか」と聞くと、「そうだ」とケロッとした顔で言うんです。そういうことが何度もありました。計算なのか、思いつきなのか。その役を生きているとしか考えられない。とにかくすごい人です。
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。