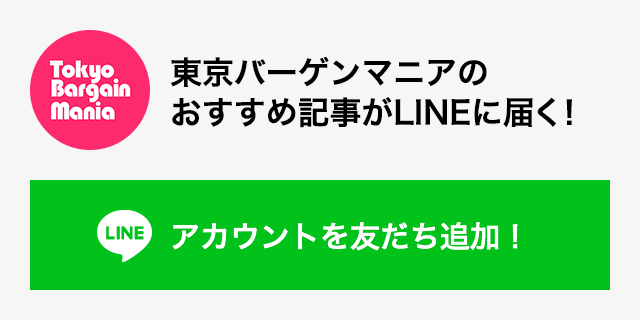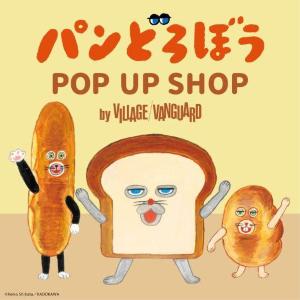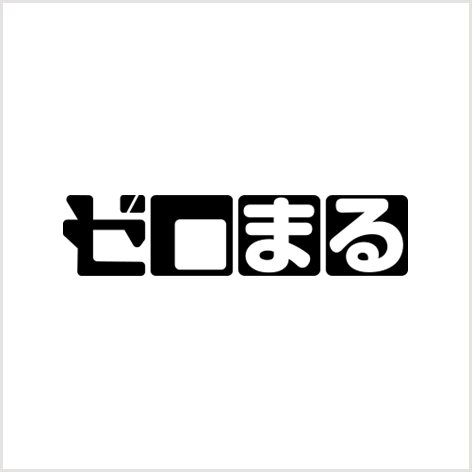映画「罪の手ざわり」/ジャ・ジャンクー監督に聞く 中国社会に潜む暴力「正面から向き合うべきだ」
中国ジャ・ジャンクー(賈樟柯)監督の新作映画「罪の手ざわり」が2014年5月31日公開される。中国で実際に起きた四つの暴力事件を題材に、社会を揺さぶる急激な変化、人々の心にひそむ闇をあぶり出し、昨年のカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した。日本公開を前に来日した監督は「なぜ彼らは追い詰められたのか。暴力に正面から向き合わなければ、暴力はなくならない」と語った。
マスメディアのニュースだけでは何かが足りない
──暴力をテーマの中心にすえた理由はなんでしょうか。
中国でここ数年、暴力事件が起きることが気になっていた。ツイッターなどインターネットを通じてニュースが次々入ってくる。まず考えたのは「昔から暴力事件はあったのに、新しいメディアのせいで増えたように感じるのだろうか」だった。考えこんでしまった。
中国の映画業界では、暴力を撮ることがあまり歓迎されない。暴力と社会は非常に密接に関係しているので、国は喜ばないんだ。ただ現状を前に、私は暴力に向き合い、思考してみたかった。
中国ではネットだけでなく新聞やテレビでももちろん暴力事件は報道される。ただ、マスメディアのニュースだけでは何かが足りない。事件については報道されるが、背景に何があり、個人がなぜ追い詰められ、こんなことが起きるに至ったのか。プライベートに関することは外されて報道されるのが普通だからだ。
私もほかの人々同様、暴力がなぜ起きるかはよく分かっていなかった。情報を集め、脚本を書き、撮影する過程を通じ、彼らが追い詰められた状況を想像する中で、リアルな理由に近づいていけたと思う。それが映画を撮る過程でもあった。暴力に正面から向き合わなければ、暴力はなくならないと思う。
──劇中登場するトラックに聖母マリア像が描かれていた。地方での宗教の現状について教えてほしい。
作品にはマリア像以外にも、いくつか宗教的なものを散りばめた。中国では政治的、歴史的な理由で信仰が中断され、断たれたと感じている。社会にある信仰に対する断絶感、欠落感を意識した。私自身は特定の宗教を信じていない。だがここ数年、宗教に注目してきた。信仰は「人間としてあるべき姿」を守ってくれている気がする。「人々は平等でなければならない」など、信仰で支えられているものは多いと思う。
──取り上げた事件を四つに決めた理由は?。
(中国の現状を表す)四つの面がはっきり見えるものを選んだ。一つ目のエピソードは明らかに社会問題が理由の暴力。二つ目は田舎町で自我を実現できない困難と貧困。「この街にいても面白くない」という言葉が根底になった事件だ。それも暴力の一つの側面だと思った。
三つ目の女性の話は、他人に自分の尊厳を傷つけられ、はぎとられた人間が、どんな反応を起こすか。人間の尊厳がテーマ。最後は人が自滅する話。暴力の方向性がほかの三つと違う。目に見えず分かりにくい暴力だ。エピソードは北から南へつないでいった。都市に受け入れられず、機械化された人間。感情的に孤立する人間。中国のどこでも起きうる事件だと思う。
(劇中描かれた労働者の自殺について)一番印象的だったのは、彼らが流動していく姿だった。中国の工場で働く人たちは昔、国営企業で福利厚生も手厚く、退職金もきちんとあった。工場と人間がつながっていた。今は人は1日ごとに入れ替わり、いなくなればすぐ補充される。工場に働く若者が帰属感を持てない。彼らがさすらう、落ち着かない気持ちがよく分かった。
工場は高度に自動化、分業化されている。労働者はすべての製造過程を知らなくてもいい。中国にはかつて「工人」という言葉があった。技術者に近いニュアンスだったが、今ではアルバイトに近い感覚。「労働者」とも異なる気がする。
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。