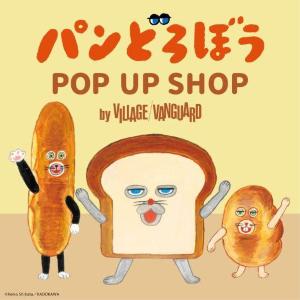福島第1原発の事故後、放射能の影響を受けた場所で、懸命に生きる人々がいる。彼らの声は我々に届いているだろうか。チェルノブイリ原発事故から30年近くたったが、今もその影響は続いている。ベラルーシの現場では、子どもたちに何が起きているのか。二つの場所で、母親たちはどう子どもを守ろうとしているのか──。
「ヒバクシャ 世界の終わりに」(03)、「六ヶ所村ラプソディー」(06)、「ミツバチの羽音と地球の回転」(10)など、核をめぐる作品を発表してきたドキュメンタリー映画監督、鎌仲ひとみ。最新作「小さき声のカノン 選択する人々」では、福島とチェルノブイリを舞台に、被爆から子どもを守る母親たちの姿に迫る。
放射能と戦うつらさが画面からひしひし伝わる
福島県二本松市。自主避難せず暮らす佐々木さん家族は、400年の歴史を持つ寺を守っている。住職の夫と暮らするりさんは、全国の支援者から野菜など食材を届けてもらい、境内で運営する幼稚園の保護者に配る。母親たちは子どもの通学に付き添い、通学路の放射線量を測る。基準値を超える場所では自主的に草をむしり除染する。
一方、ベラルーシでは事故から30年近くが経過していた。監督は事故現場近くの町に向かい、当時子どもだった人たちに話を聞き、データを検証する。子どもの健康を守るため、放射能の影響がない場所へ移動して合宿する「保養」。支援団体「チェルノブイリの子どもを救おう」代表で小児科医のスモルニコワさんの活動を追っていく。
取材テープは400時間以上。監督自身がレポーターとナレーターを務め、非常に柔らかい語り口で報告は続く。しかし、その内容は濃密だ。記録映像や検証データには衝撃を受ける。「自分も被曝したのでは」と錯覚を覚えるほどに──。
福島では今日も放射能が漏れ続けている。母親たちは覚悟と葛藤の中、子どもの前では笑顔を絶やさない。しかし、監督が一人ひとりに話を聞くと、みな涙を流し、苦しい胸の内を吐露する。放射能と戦うつらさが画面からひしひし伝わってくる。事故からまもなく4年。現実を真正面から直視し、力強いメッセージを込めたドキュメンタリー映画だ。
「小さき声のカノン 選択する人々」(2014年、日本)
監督:鎌仲ひとみ
2014年3月7日(土)、シアターイメージフォーラムほかで全国順次公開。作品の詳細は公式サイトで。
記事提供:映画の森
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。