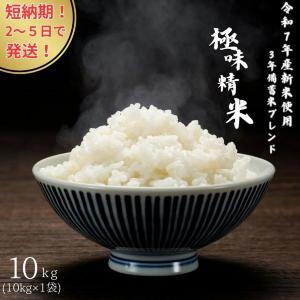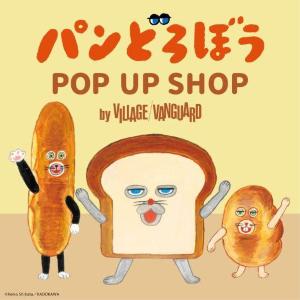「映画という島を離れて生きる自分は、想像できない」
――冒頭に映画館のショットがあります。観客の存在をどう考えているのでしょう。
映画を作る時、観客は頭にいません。むしろ自分自身について考えます。冒頭のショットは、今見ている光景に似ています。あの映画館の席では、全員眠っているか、死んでいるか判然としない。作品の構想ではいつも映像がひらめく。今回は映画館のショットだった。私は観客が何者かよく理解できない。分かるのは相当な人数の集団で、まもなく全員が死んでいくことだけ。
――オスカーをリムジンで運ぶ運転手のセリーヌ。映画でどんな役割を果たしているでしょう。
パリに住む中国人は、結婚式によくリムジンを使います。しかし私には大きな棺桶に見える。不吉であると同時に、エロチックでもある。リムジンを物語の中心に置き、中の人々を想像しました。彼らはリムジンを時間決めでレンタルしていて、借りている間だけ、何かの役を演じているのです。自分を金持ちに見せるため、有名人に見せるため、あるいは自分を隠すため、リムジンを使っている。
そこで思いついた。限られた時間だけでなく、いつもリムジンに乗り、人格を絶えず変えながら、さまざまな役を演じていく人物を。問題は誰が運転するか。そこで昔の幻想的なフランス映画を思い出した。ルイ・フイヤード、ジョルジュ・フランジュの映画などです。フランジュの「顔のない眼」(59)は、当時20歳のエディット・スコブが主演しました。「ポンヌフの恋人」にも出てもらったが、編集で削られ、作品に残ったのは髪の毛だけ。だから彼女でもう1本撮ろうと思ったんです。
セリーヌ役への起用にはそんな事情もあるが、役割が何かは私にも謎です。運転手だが秘書のようでもある。物語が展開するにつれ、次第に権威的な存在になっていく。車の鍵もお金も持っている。なぜそうなったか。自分でも説明できません。
――現在あなたのように映画と真摯に向き合う作家は少ないと思う。映画に対してどんな責任を感じていますか。
映画の発明は奇跡のようです。人間に発明された芸術は映画だけ。17歳で映画に出合えて、とても幸運だった。地上に映画という島がある。島からは生と死を別の角度で見られる。私の作品は少ないが、映画という島に住んでいる。島は大きな美しい墓場でもある。住人として私に責任があるとすれば、島に眠る死者たちに対し、時々名誉を返してあげることではないでしょうか。確か(作家のジャン・)コクトーが「映画は働いている死者を撮影する」と言いました。私は島から離れて生きる自分を想像できません。
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。