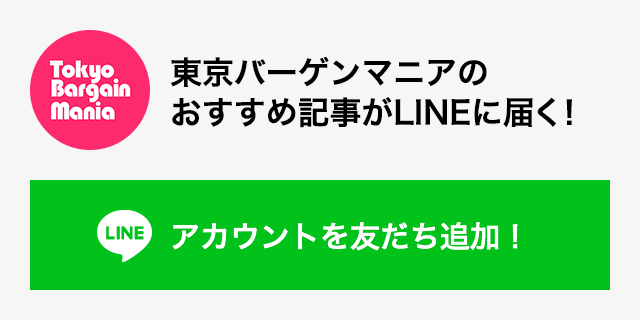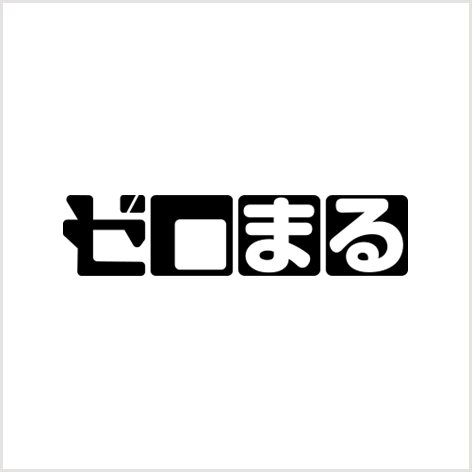映画「断食芸人」足立正生監督に聞く/檻の中の主人公と檻の外の人々。どちらが自由なのか
戦術も戦略もないと言うが、声を出すだけでもいいじゃないか
冒頭の映像がショッキングだ。東日本大震災の大津波、がれきの山、そして福島原発の爆発。悪夢のような記録映像が続いた後、日の丸を背景に、カメラに向かい怒りとも恨みともつかぬ眼差しを向ける人々の顔が映し出される。何も語らず、ひたすら前を見つめる視線の強さ。バックには「4年前、山の麓で狼に出会った......」のナレーションが流れる。魯迅「阿Q正伝」の最終章からの引用だ。4年前とは、もちろん2011年3月11日を指している。
「3.11で日本の政治的、経済的構造の根底が脆弱であることが明らかになった。もともと原発は原爆と同じ地獄の釜だ。多くの人はそれに蓋をして過疎化する村を救いたいとか、未来志向の顔でごまかしながらやってきた。そういう人たちは、あれだけの死者、行方不明者、被爆者を前にして、もはやメッセージなど発することはできない。ただ、怨嗟(えんさ)の眼差しだけが彼らの気持ちを表しているのだ」
いかにものんきそうなBGMに乗って商店街に現れる主人公だが、実は心の内に言葉にならぬものを抱えているのかもしれない。冒頭の映像は、そんな想像をかき立てもする。
足立監督が"紙芝居"と呼ぶこの映画。出演者たちのキャラクターの濃さは確かに芝居的である。中でも印象的なのが、主人公を断食芸人にして使い捨てていく興行師と呼び込みの男。
「興行師は桜井大造さん。映画に出るのは初めてだが、台湾で長年にわたり劇団活動を展開し、アジアでは演劇王として有名だ。大造さんには、権力をかさにきるのではない形で、権力者を演じてくれと注文したら、"分かった、ヒトラーをやればいいんだな"と。たちまち理解してくれて、口ひげに七三分けで、望み通りの芝居をしてくれた。大造さんも、呼び込み屋の流山児祥さんも、女医の伊藤弘子もそうだが、テント芝居、アングラ芝居をやっていた人たちが右往左往するような映画にしようと思った。かなりの部分はアテ書きした」
「若者のすることは100%支持する」と言い切る足立監督。若い男女の物語に希望の光を当てたのは、若者への期待の現われだろう。
「たとえばSEALs(シールズ)をみんな批判するが、やっと声を出した若者をなぜ悪く言うのか。戦術も戦略もないと言うが、声を出すだけでもいいじゃないか」
撮影が終わった後、国会前で大学生がハンストを始めたので、連帯の挨拶に行った。
「"何を撮っているのか"って聞くから"カフカの『断食芸人』だ"って答えた。すると、カフカって誰ですかって言う。それから、断食芸人と書いてあるのを見て"だんしょく芸人"って読む若者もいた。でも、考えてみれば、カフカなんて知らなくてもいい。断食をだんしょくって読んだって構わない。ギャップがあるからこそ連帯する意味があるのであって、ギャップがなかったら映画を作る意味もない。当たり前に受け取られるものを見せてもしかたがない。摩擦や衝突があってこそ、初めて違いが分かり、お互いのことを意識し合えるんだ」
摩擦や衝突は大歓迎だそうだ。カフカをはじめ、魯迅、聖書、吉増剛造、玉音放送、死のう団......。若者には馴染みの薄い文学作品や映像、史実が大量に引用される本作。どこまで伝わるか、あるいは伝わらないまでも楽しんでもらえるか。上映後のイベントで、若者の生の声が聞けることを期待している。
監督:足立正生
出演:山本浩司、桜井大造、流山児祥、本多章一、伊藤弘子、井端珠里、吉増剛造、和田周、川本三吉、田口トモロヲ(ナレーション)
2016年2月27日(土)、渋谷ユーロスペースほかで全国公開。作品の詳細は公式サイトまで。
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。