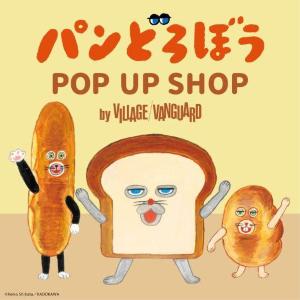日本の空の玄関口、成田国際空港。1978年に開港して36年たつが、建設計画はいまだに完了していない。周囲では今も機動隊による検問が続いている。反対闘争は終わったわけではないのだ。
始まりは66年。政府は当初候補にも挙げていなかった成田市三里塚を空港建設地に指定する。御料牧場のあったため、用地買収が容易に進むとの目算だった。だが読みは外れる。地元農民の一部は、空港建設に抵抗。"ニッポン最後の百姓一揆"と呼ばれた三里塚闘争(成田闘争)が幕を開けた。
67年には新左翼各派が支援に加わり、闘争は急速に先鋭化していく。多数の死傷者が出る中、国側は計画を大幅に縮小して開港を強行。90年代に入ると、空港公団からの働きかけにより、抵抗を続けていた農民も次々と収用に応じていった。
現在もなお買収工作に屈せず、静かなる抵抗を続ける人々。土地を手放し、新たな生活に踏み出した人々。「三里塚に生きる」は、その両方の姿をとらえたドキュメンタリーである。
今まさに福島や普天間で同じことが起きている
飛行機が爆音を響かせる青空の下、ひとり黙々と畑を耕すのは、元青年行動隊のリーダー柳川秀夫だ。闘う男のイメージはなく、穏やかな微笑みを浮かべる。だが、訥々(とつとつ)と語られる言葉からは、半端でない苦労や覚悟が伝わってくる。
「(自殺した同志)三ノ宮文男の遺書は『三里塚にいきつづけろ』と言っている。あれは『闘え』ってことだっぺ。だから、まじめに受け取るしかねえべ」。三ノ宮の遺言は、柳川の運命を決定づけた。
一方、元婦人行動隊の椿たかは、「こんなに犠牲者を出すなら、早く移転したほうがよかった」と、長すぎた抵抗運動を後悔する。「国の側も人が死ぬ、反対派同盟側も人が死ぬ。にっちもさっちも行かなくなる。どちらもあきらめない」と泥沼の日々を振り返るのは、元青年行動隊の石毛博道だ。
どちらが正しいかを問うているのではない。人生を狂わされた点では同じだ。映画は現在の彼らを映し出すとともに、60年代、70年代に小川プロダクションが手がけた「三里塚」シリーズや未公開映像に収められた若き日の姿も見せてくれる。"静"と"動"、"穏"と"乱"。厳然とした月日の流れ。しかし、静穏の中にも闘争の炎は燃え続ける。その火を絶やしてはならないと思う。今まさに福島や普天間で同じことが起きているからだ。
「三里塚に生きる」(2014年、日本)
監督:大津幸四郎・代島治彦
2014年11月22日(土)、ユーロスペースほかで全国公開。作品の詳細は公式サイトまで。
記事提供:映画の森
* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。